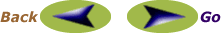美しき人倫共同体から散文的な近代へ1
美しき人倫共同体から散文的な近代へ
- イエナ期ヘーゲルのフィヒテ受容

G.W.F.Hegel
序
美しき人倫、美と善の融合した美しき共同体はいつの世にも人々の夢だった。たとえば昨年大ブームだった宮沢賢治の「羅須地人協会」がそうだし、その思想的綱領である『農民芸術概論綱要』には美・表現と善が融合した共同体が高らかに謳いあげられている。
資本主義と帝国主義の醜悪さが蔓延したヴィクトリア朝イギリスには、ラスキンとモリスに率いられたアーツ・アンド・クラフツ運動がある。工芸や職人の共同体に理想を見て、芸術と労働が花開く共同体を夢見た。これらのイメージは、初期のマルクス・エンゲルスの共産主義の夢を規定し、芸術・表現的な人間の解放イメージを『経済学・哲学草稿』や『ドイツ・イデオロギー』に描き出さざるをえなかった。モリスの『ユートピア便り』に描かれたそのオルタナティヴな農村的ユートピアは、管理的な社会主義が崩壊した今こそ、再評価の価値があるだろう。
これに触発されたドイツのバウハウス、あるいは日本の柳宋悦の民衆的工芸運動も、人類がつかの間夢見た美的な共同体の模索例である。現在、先進国のあちこちで試みられているオルタナティヴな共同体や芸術家村、あるいは発展途上国で地域の民俗芸能や演劇をもとにして地域のアイデンティティーを確立しようとする試みもその幸福な例にあたるかもしれない。このような試みの思想的な営為として古典的なものが、ドイツ観念論とドイツ・ロマン主義である。それは人類の抱いた見果てぬ夢のひとつの理念型として、吟味に価するものではないだろうか。
若き時代が美しく、理想に輝いて、美と善が意識せずに合一していたのは、人類の歴史だけではなく、個人にも当てはまる。 ドイツ観念論とその周辺がふつふつとイエナを中心にたぎっていたころ、ゲーテ、シラ−、フィヒテ、そして若きヘルダーリン、へ−ゲル、シェリングたちの胸を去来していたのは、ギリシャの古典的人倫とその理念を無媒介に近代へともたらしたフランス革命であったろう(ゲーテはかなりあやしいとしても)。
ドイツの後進性としてよく語られることだが、直接にローマの共和制の伝統に由来をもつフランスと異なって、そうした伝統をもたないドイツは、ギリシャとつながることで、そのコンプレックスを解消しようとした。ドイツにおけるギリシャ像の理想化はフンボルトにその頂点を見る独自のドイツ人文主義の伝統を形成した。彼らは理想化されたギリシャからフランス革命をみようとしていたのである。
人類の青年時代のギリシャの人倫が、美と善との融合した共同体として語られるのと軌を一にして、青年時代のヘーゲルがヘルダーリンと共にもとめたのは、理念としてのギリシャを範にした美と善との融合した共同体だった。その理想を二人が著したものが『ドイツ観念論最古の体系プログラム』(1796/97)である(1)。
シラーの「美的国家論」、フィヒテの『フランス革命論』の思想を受けて、国家理念の非存在、それは「機械的な歯車じかけ」であり、マルクスに先んじて、国家は死滅しなけれぱならないと説く。美の理念こそがあらゆる理念を合一し、「真と善は美においてのみ姉妹となる」(2)。
ここにあらわされたような傾向は、イエナ期に入っても引き続く。『自然法批判論文』や『人倫の体系』では周知のように、ギリシャ的人倫を範として、それを人倫の絶対的理念とし、個別性を否定的なものとして扱った。
人倫は「もしそれが個別者の魂でなければ、個別者の中に自分を表現することはできない。個別者の魂であるのは人倫がただひとつの普遍的なものであり、民族の純粋な精神であるかぎりのことである。肯定的なもの(人倫)はその本性上、否定的なもの(個別者)よりも先である。ちょうどアリストテレスが民族は本性上、個別者よりも先であるといっているように」(3)。
個別者は、自己の否定により、民族と調和する。死の危険を通じてのみ、英雄的個人(自由身分)は民族と一体になる。非自由人は労働と農耕に従事して全体を生かす。あらゆるものがいきいきと調和しあい、生気を与えあって、生きた有機体となる。
「対立や経験的なもの、現象などは絶対的直観のうちへと落ちてゆき、それらはただ遊戯(Spielen)としておのれを表現する」(4)。
あらゆるものが契機となり、全体を成り立たしめ、合目的的に調和し、自己内対立でさえ、人倫の悲劇として上演(シュピーレン)され、「運命」という名の必然性に統制されるのであれば、それを見ている者には意にかなうものであろう。それはまさしくソフォクレスらの悲劇に比肩する「美しき芸術作品」としての共同体である。
「古代においては美しき公的な生は万人の習俗であり、普遍と個別の直接的な統一としての美でもあり、ひとつの芸術作品であった」(5)。
しかし、個別者が全体の契機となり、全体は有機的に調和して、美と人倫が融合した共同体構想は、イエナ後期には放棄される。かつては個別性は、全体を揺るがす否定的なものとして位置付けられ、全体の契機に過ぎなかったが、いまや、個別性そのものが絶対的となる。
「各人は完全に自己のうちへと還帰し、彼の自己そのものを本質として知り、定在する普遍者から分離されつつも、絶対的であり、彼の知において絶対者を直接的に所有しているという我意にいたっている」(6)。
この「知」というエレメントのうちへ精神は歩みいり、「知」として、万人の自己に自らの定在を持つようになる。個別者は知のうちに絶対者を見、精神は知としてのあり方を自らの実存形態とする。ヘーゲルによれば、これはギリシャを離れた「北方の原理」、すなわち内面の無限、主観性に立ち返ったキリスト教を経たゲルマンの原理である。
精神が、このように直接的な定在から純化されて、対象的な知のうちに住むのであれば、「定在する個別性に対して無関心となり」(7)、ギリシャのような全体と個別、「普遍と個別との直接的統一としての美」(8)はありえない。精神は自らの美しい定在を脱ぎ捨てて「学」という名の散文的な形態をまとう。
『体系プログラム』でうたわれたヘルダーリンの「ポエジー」はもはや最高のものではありえない。哲学者には詩人と同等の美の力はもはや必要でなくなった。ギリシャの官能的な陽光の中で感性を解放させるのではなく、ファウストが「灰色の学問」と嘆いたように、暗いかび臭い書斎や大学の中で老いた哲学者に甘んじたほうが、処世術としては賢明なのだ。 壊れやすい美しき魂が現実の不条理とぶつかり、耐えきれず錯乱し、塔の中に住むよりは、精神の運動を知として捉え、それをありのままに、各人の死を賭けた戦いですら、必然・狡智として叙述することが哲学者の使命となる。
ヘーゲルのこのような変化は表向きは、つとに『精神現象学』の序文で有名である。だが、精神が人倫の形態を脱ぎ捨てて、知のエレメントヘ歩みいるという変化の過程、その苦闘を示すものは、『イエナ期体系構想草稿』と呼ばれるものなのだ。
シェリングやヘルダーリンの影響を受けて、スピノザの自然とアリストテレスの目的論的な自然概念の混交したそれ自ら生成する自然、その顕在態としての人倫共同体という立場から、カント、フィヒテ的な近代の自己意識は悪しき個別性だと、『差異論文』や『自然法批判論文』で批判していたヘーゲルは、『体系構想 I(1803/4)』でそれが揺らぎ始め、『体系構想 III(1805/6)』で完全にその影響圏から脱してしまう。
その際、大きく寄与したものがイギリス国民経済学研究とフィヒテの自然法研究だった。とくに『体系構想 I(1803/4)』から『体系構想 III(1805/6)』への大きな変化にはフィヒテの再発見が関与している。
この点に関しては、これまでフィヒテの相互承認論がへーゲルの相互承認論を導いたという文脈で、いくつかの研究が出ている(9)が、承認論に限定することはヘーゲルからフィヒテを見てしまうことになる。
フィヒテのいかなる部分がヘーゲルの思想確立に力があったのか、ここではあくまでも、当時の彼らの思想的宣言である『ドイツ観念論最古の体系プログラム』にそった形で、つまり美と共同体、人間のいきいきとした絆、コミュニケーションの可能性をめぐる文脈において、検討していくべきだろう。(続く)
注
(1)F.W.J. Schelling, Text zur Philosophie der Kunst, Reclam 5777(3). S. 96-97. 邦訳はドイツ・ロマン派全集第9巻『無限への憧憬』国書刊行会 97ページを参照のこと。なお、私は作者説については、ヘルダーリンが主たるモチーフの作者で、ヘーゲルがそれを筆写したという立場をとる。
(2)A.a.O(同上).
(3)"Ueber die wissenschaftslichen Behandlungsarten des Naturrechts(自然法批判論文)"
in : Hegels Werke , Suhrkamp, Bd. 2. S. 505
(4)System der Sittlichkeit(人倫の体系), PhB. 144a, S. 53-54 (5)"Systementwurf III(体系構想
III )" in: Hegel Gesammmelte Werke, Bd. 8. 1976. S. 236
(6)Dasselbe(同書).S.262
(7)Dasselbe. S. 265
(8)Dasselbe. S. 263
(9)たとえば、M.リーデル「ヘーゲルの自然法批判」(『ヘーゲル法哲学』清水正徳、山本道雄訳、福村出版、1976年)、L. Siep, Anerkennung
als Prinzip der praktischen Philosophie, Freiburg/Muenchen, 1979. および、高田純「承認論の転換」(『哲学』第39巻、1989年)、他者論という形では、入江幸男「フィヒテとヘーゲルの他者論」(大阪大学文学部『哲学論叢』第15号、1985年など。Siepの書はこの問題の古典的なものだが、やや議論が荒い面がある。全体的な把握ではリーデルの方がすぐれていると思う。高田純のこの問題の集大成である著書『承認と自由』は未見なので、何ともいえない。